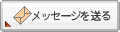2012年04月06日
東京物見遊山 その2 キム・ギドク監督映画 「アリラン」
渋谷にある 「イメージフォーラム」 と言うところで、 キム・ギドク監督映画 「アリラン」 を見てきた。
この 「イメージフォ-ラム」 というシアターは、 建物自体も 館内も、 こじんまりとしていて、 ちょっと個性的で、 素敵な感じがするところだった。 上映されている映画も、 メジャーなものとは 一線を画しているようで、 「オーナーが 見せたいと思う映画」、 「じぶん達こそが 上映しなくてはならない映画」、 の選りすぐりを 厳選しているような印象を受けた。
なにか 期せずして 上質な空間と 出会った 感じだった。

実は 「アリラン」 と言う映画は、 新聞の映評を読んで 見てみたいと思った 映画だった。
キム・ギドク氏といえば 映画 「春夏秋冬、そして春」 の監督である。
その彼が 「悲夢」 の撮影中に起きた事故や、 人間関係の軋轢などもあって、 映画を撮れなくなり、3年間 山の掘っ立て小屋に ひとり 立てこもり 暮らしていたそうなのだが、 そのときの 自身の姿を、 自分自身で 撮ったのが まさに この映画である。

「春夏秋冬 そして春」 と言う映画は 映像がもの凄くきれいで、 その印象が強く残っている映画だ。
湖に浮かぶ 小さい古寺が舞台となっていて、 周囲が織りなす自然と 四季の移ろい、 そして 一人の人間の一生が、 耽美的に 情感豊かに そして神秘的に描かれ、 「映画」と言うよりは まるで 「芸術」 を見せられているような 不思議な 映画だった。
この映画は 海外の国際映画祭でも さまざまな賞を うけている。
キム・ギドク監督は、 韓国国内よりは むしろ 国際的に 名声を得ているようだ。

さて 「アリラン」 という 映画。 てっきり 自身の苦悩する姿 そのままの ドキュメンタリー調かと思いきや 全然そうではなった。
詳しいいきさつはわからないけれど、 (アジュンマの 勝手な推察だが、) 最初は 普通に撮り始めたのかもしれない。
だが 撮り始めたらば最後、 もう次から次へと 勝手に アイデアが浮かび、 こうしよう、 つぎはああしようと、 内から 湧き出るエネルギーのままに、 結局は 映画作りに のめり込んでいってしまった のではないだろうか?
単なる撮影者ではなく、 監督となって、 キム・ギドクという人間を キム・ギドク監督が 映画にしてしまった、 そんな感じのする映画だった。

たとえば、ストーブで 魚を焼いて食べるシーン。
魚を焼く 手元のアップがあり、 ムシャムシャと食べている 口元のアップもある。
座り込んで ただただ食べ続けている後ろからの姿も 映され、
おいしいんだか おいしくないんだかはっきりしない 顔のアップもある。
魚を食べるシーンだけでも こうした さまざまなアングルから 撮られているのである。
普通の映画であれば、 なんでもないような ワンシーンであるが、 これをたった一人で すべてやった、 と 想像したらどうなるだろうか?
相当どころか かなり 入れ込まないと とうてい できない作業だと思う。
自分の代わりになる なにか目標物を置き、 それが焦点となるように カメラのセッティングをしてから、 そこに自身を移動して 主演者として座りなおす。
そのシーンが終わると またカメラを 移動し、 同じように繰り返す。
レンズの先に 自身の 手元など アップの部分が来るように うまく 食べなくてはいけない。 そしてまたカメラを移動し また食べるの繰り返し。
むしゃむしゃと 魚を食べているシーン、 いかにも 無心に 勢いよく食べているように 映画にはなっているが、 実際は おちおち 魚を食べているどころではなかったはずだ と思う。
ひょっとして 何回か 同じ魚を焼いて食べたんじゃないか? とまで思ってしまう。

こうしたシーンが これ全編に 続いている。
外で 用を足しに行くシーン、 エスプレッソの機械を 自ら作り、 コーヒーを 搾り出して それをおいしそうに 飲むシーン などなど、
アングルに懲り 背景に懲り、 そうして 一つ一つの行為に メッセージをこめる。
はっきりいって ドキュメンタリーの 枠を 完全に超えている。
後半、 葛藤する 主演者の キム・ギドク氏と、 それを揶揄する 第二のキム・ギドク氏が 出てきて、
かと思うと またその二人を写したフィルムを 見ながら、 何やかやと言っている監督目線の キム・ギドク氏が、 同時に写っていたりもする。
もう、こりにこっているのである。
最後は 銃を作って発砲するという 象徴的なシーンもあって、 なにやら 完全な 「映画」 となって完成していた。

あ~、 物を創りだす、 と言うのは こういうことなんだ。
創造していく人ってのは こうなんだぁ。
映画を 見終えて 真っ先に 思ったことである。
およそ、 芸術家と言われる人たちは、 もちろん それぞれ 違いはするだろうけれど、 多かれ少なかれ、 自身の中からどうしても 表現しないではいられない何かに 突き動かされての 作品を 世に 送り出しているのだろう。
それが 音楽であったり、 絵であったり、 彫刻であったり、 芝居であったり、 物づくりであったり、 物書きであったり、 そして 映画であったり するのではないだろうか?
「アリラン」という映画、
「凡人にはない 何かを 持った人間」 を 生々しく、 いきなり強烈に 見せつけられてしまった。
そんな 感じのする 映画だった。


この 「イメージフォ-ラム」 というシアターは、 建物自体も 館内も、 こじんまりとしていて、 ちょっと個性的で、 素敵な感じがするところだった。 上映されている映画も、 メジャーなものとは 一線を画しているようで、 「オーナーが 見せたいと思う映画」、 「じぶん達こそが 上映しなくてはならない映画」、 の選りすぐりを 厳選しているような印象を受けた。
なにか 期せずして 上質な空間と 出会った 感じだった。
甲府に行ってきた
どこを歩いていても 富士山が 真近に くっきりと現われ ドキッとする。
やはり 富士は 日本一の山だと実感
どこを歩いていても 富士山が 真近に くっきりと現われ ドキッとする。
やはり 富士は 日本一の山だと実感
実は 「アリラン」 と言う映画は、 新聞の映評を読んで 見てみたいと思った 映画だった。
キム・ギドク氏といえば 映画 「春夏秋冬、そして春」 の監督である。
その彼が 「悲夢」 の撮影中に起きた事故や、 人間関係の軋轢などもあって、 映画を撮れなくなり、3年間 山の掘っ立て小屋に ひとり 立てこもり 暮らしていたそうなのだが、 そのときの 自身の姿を、 自分自身で 撮ったのが まさに この映画である。
甲府にある昇仙峡。
早春の渓谷を眺めながらの散策。
まだ気温も低く 見も心も引き締まるような 美しさだった。
早春の渓谷を眺めながらの散策。
まだ気温も低く 見も心も引き締まるような 美しさだった。
「春夏秋冬 そして春」 と言う映画は 映像がもの凄くきれいで、 その印象が強く残っている映画だ。
湖に浮かぶ 小さい古寺が舞台となっていて、 周囲が織りなす自然と 四季の移ろい、 そして 一人の人間の一生が、 耽美的に 情感豊かに そして神秘的に描かれ、 「映画」と言うよりは まるで 「芸術」 を見せられているような 不思議な 映画だった。
この映画は 海外の国際映画祭でも さまざまな賞を うけている。
キム・ギドク監督は、 韓国国内よりは むしろ 国際的に 名声を得ているようだ。
渓谷を眺めながら、甲府の名物 「ほうとう」 をたべる。
味噌味で 山菜がたっぷり入っている。
味噌味で 山菜がたっぷり入っている。
さて 「アリラン」 という 映画。 てっきり 自身の苦悩する姿 そのままの ドキュメンタリー調かと思いきや 全然そうではなった。
詳しいいきさつはわからないけれど、 (アジュンマの 勝手な推察だが、) 最初は 普通に撮り始めたのかもしれない。
だが 撮り始めたらば最後、 もう次から次へと 勝手に アイデアが浮かび、 こうしよう、 つぎはああしようと、 内から 湧き出るエネルギーのままに、 結局は 映画作りに のめり込んでいってしまった のではないだろうか?
単なる撮影者ではなく、 監督となって、 キム・ギドクという人間を キム・ギドク監督が 映画にしてしまった、 そんな感じのする映画だった。
武田信玄神社。
甲府駅から 10分、 とあったので 歩いたが、歩けど歩けど たどり着かない。
よく見たら 車で10分だった。
おかげで 甲斐の街が 実感できた。
甲府駅から 10分、 とあったので 歩いたが、歩けど歩けど たどり着かない。
よく見たら 車で10分だった。
おかげで 甲斐の街が 実感できた。
たとえば、ストーブで 魚を焼いて食べるシーン。
魚を焼く 手元のアップがあり、 ムシャムシャと食べている 口元のアップもある。
座り込んで ただただ食べ続けている後ろからの姿も 映され、
おいしいんだか おいしくないんだかはっきりしない 顔のアップもある。
魚を食べるシーンだけでも こうした さまざまなアングルから 撮られているのである。
普通の映画であれば、 なんでもないような ワンシーンであるが、 これをたった一人で すべてやった、 と 想像したらどうなるだろうか?
相当どころか かなり 入れ込まないと とうてい できない作業だと思う。
自分の代わりになる なにか目標物を置き、 それが焦点となるように カメラのセッティングをしてから、 そこに自身を移動して 主演者として座りなおす。
そのシーンが終わると またカメラを 移動し、 同じように繰り返す。
レンズの先に 自身の 手元など アップの部分が来るように うまく 食べなくてはいけない。 そしてまたカメラを移動し また食べるの繰り返し。
むしゃむしゃと 魚を食べているシーン、 いかにも 無心に 勢いよく食べているように 映画にはなっているが、 実際は おちおち 魚を食べているどころではなかったはずだ と思う。
ひょっとして 何回か 同じ魚を焼いて食べたんじゃないか? とまで思ってしまう。
宿泊は 湯村温泉の 「旅館明治」
太宰治が ここの旅館で 執筆もしていたと言う 「太宰ゆかりの宿」だった。
太宰の奥さんは 甲府の方のようで
結婚写真をはじめ 太宰関連の資料コーナーもあった
太宰治が ここの旅館で 執筆もしていたと言う 「太宰ゆかりの宿」だった。
太宰の奥さんは 甲府の方のようで
結婚写真をはじめ 太宰関連の資料コーナーもあった
こうしたシーンが これ全編に 続いている。
外で 用を足しに行くシーン、 エスプレッソの機械を 自ら作り、 コーヒーを 搾り出して それをおいしそうに 飲むシーン などなど、
アングルに懲り 背景に懲り、 そうして 一つ一つの行為に メッセージをこめる。
はっきりいって ドキュメンタリーの 枠を 完全に超えている。
後半、 葛藤する 主演者の キム・ギドク氏と、 それを揶揄する 第二のキム・ギドク氏が 出てきて、
かと思うと またその二人を写したフィルムを 見ながら、 何やかやと言っている監督目線の キム・ギドク氏が、 同時に写っていたりもする。
もう、こりにこっているのである。
最後は 銃を作って発砲するという 象徴的なシーンもあって、 なにやら 完全な 「映画」 となって完成していた。
甲府にも 「平和通り」 がありました
あ~、 物を創りだす、 と言うのは こういうことなんだ。
創造していく人ってのは こうなんだぁ。
映画を 見終えて 真っ先に 思ったことである。
およそ、 芸術家と言われる人たちは、 もちろん それぞれ 違いはするだろうけれど、 多かれ少なかれ、 自身の中からどうしても 表現しないではいられない何かに 突き動かされての 作品を 世に 送り出しているのだろう。
それが 音楽であったり、 絵であったり、 彫刻であったり、 芝居であったり、 物づくりであったり、 物書きであったり、 そして 映画であったり するのではないだろうか?
「アリラン」という映画、
「凡人にはない 何かを 持った人間」 を 生々しく、 いきなり強烈に 見せつけられてしまった。
そんな 感じのする 映画だった。
Posted by アジュンマふきこ at 01:07│Comments(0)
│韓国映画